仮免許証を交付されると、路上を走ることができるようになります。
そして交付の時、同時に路上申告書というものをもらいます。
この路上申告書は本免許学科試験を受けるまでに5日間、
1日2時間を目安に運転の練習をした内容を、記載する書類になります。
これがないと学科試験を受けることができません。 練習はどうやるの?
教習所に通わなければならないの?
と思いがちですが、
条件をしっかり守ってやれば、御自身でやることも可能です。
ポイントは簡潔に3つです
・御家族や御友人に車を借りる。
・助手席に免許を取って3年以上経っている方に同乗してもらう。
・A4のコピー用紙に仮免許練習中と印字し、車体の前後に貼り付ける。
先ず、御家族や御友人でお車を持っている方に車を借ります。
その理由は、レンタカーは不可になっているからです。
必ず御家族や御友人に頼んでください。
路上申告書に記載する際に、車体の番号が必要になってまいります。
レンタカーでは通りませんので、必ず借りるようにしてください。
練習中は助手席に、免許を取って3年以上が経っている方に同乗してもらいます。
御家族、御友人で、免許を取ってから運転していない方でも、
3年以上経っていれば可能です。
車体には、A4のコピー用紙に仮免許練習中と印字し、それを前後に貼り付けます。
プレートは法律通りの仕様にすれば、自作することが可能です。
「道路交通法施行規則/別記様式第十一」ではプレートの仕様を次のように規定しています。

※埼玉県警察HPより画像引用
板の大きさ:縦170mm×横300mm
板の材質:金属、木その他の材料を用い、使用に十分耐えるものとする。
地は白色。
「仮免許」のそれぞれの文字 大きさ:縦40mm×横40mm、太さ:5mm、色:黒色。
「練習中」のそれぞれの文字 大きさ:縦80mm×横70mm、太さ:8mm、色:黒色。
プレートの一行目に「仮免許」、二行目に「練習中」と記載する。
耐水性の紙へ印刷するのもいいかと思います。
練習中は必ずつけるようにしてください。
仮免許のプレートは地上から0.4m以上、1.2m以下の位置に、
前方・後方から見やすいように表示することが義務づけられていますので必ず守るようにしてください。
このとき、ナンバープレートやウィンカー、尾灯、
ナンバー灯などを隠さないように気を付けましょう。
これで準備は完了です。
練習場所としましては、まずはあまり人通りや車通りが少ないところを探しましょう。
普段過ごしているところで、人が少ない時間などを狙うのがポイントです。
人通りが少ない時間とはいえ、いきなり夜間の練習ですと、
急な飛び出しに慌てる場合もありますので、朝早く、
明るくなってからの時間やお昼間が良いかと思います。
ですが、場所によっては通勤で車が多く通っていたり、
登校する学生が多く歩いている場所もあると思いますので、走行の際は必ず気を付けるようにしましょう。
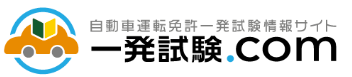
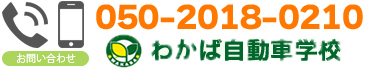
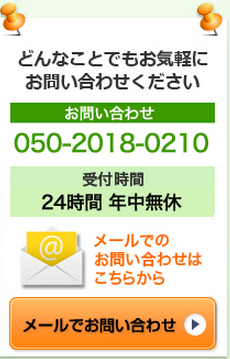

 合宿免許のメリット
合宿免許のメリット 合宿免許の遊び方ナビ
合宿免許の遊び方ナビ ご予約から入校まで
ご予約から入校まで
 会社概要
会社概要